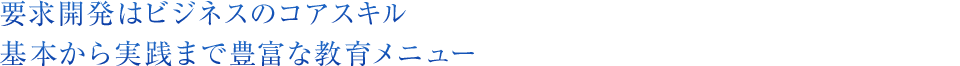要求開発トップ > 教育・セミナー
要求開発の意義は、新たな価値を発見しビジネスを再構築することにあり、情報システム構築にとどまらずビジネスのコアスキルとしても有効な手法です。
NDSでは要求開発に必要な知識や実践方法を、初心者からプロジェクトマネージャクラスまでが理解・実践いただけるよう充実した教育・セミナーを実施。
多くの受講者が要求開発の実践家として企業内で活躍されておられます。
2024年6月よりe-ラーニングのご提供を始めました。
e-ラーニングコンテンツは随時拡充してまいります。e-ラーニングは売り切り型の動画ダウンロード販売になります。
ご購入をご希望の場合、お問い合わせページより、弊社担当者までお問い合わせください。
■公開講座(GKI社、IT-X、他)
初心者の方からでも受講いただける教育セミナーを開催しております。また、同一の内容、一部カスタマイズした内容で、オンサイトでの実施についても可能です。
オンサイトでの実施をご希望の方は、お問い合わせページより、弊社担当者までお問い合わせください。
株式会社GKI社の講座にて受講ご希望の方は、こちらからご確認ください。
IT-Xの講座にて受講ご希望の方は、こちらからご確認ください。
| 開催日 所要時間 |
講座タイトル | コース内容 |
|---|---|---|
|
GKI社:応談 一社研修:応談 IT-X:開催無し 1日(6.5~7.0H) |
要求開発方法論入門 |
本セミナーでは、特に要件定義などの上流工程テクニックを身に付けたいと考えているITエンジニア様や、プロジェクトの失敗を減らしたいプロジェクトリーダー様向けに、演習を交えた講義を行います。ユーザー企業の情報システム部門の方で、IT活用を検討する立場の方にもお勧めします。
本講義を受講することで、漠然としたユーザー要求を見える化する手法や現状業務の見える化、新業務のデザイン手法などを身に付けていただけます。
本コースでは要求開発方法論において最も重要となる「準備フェーズ」のテクニックを中心に解説します。特にシステム開発者として顧客に対する提案業務や、要件定義でのユーザー要求の分析などは、その後のシステム開発プロジェクトの遂行に大きな影響を及ぼします。このフェーズをしっかりと行い、ユーザー/開発者の間できちんと合意形成できるかが要求開発のキモになります。 これらのテクニックをちゃんと学ぼうと考えると2~3日の教育コースの受講とそれなりの経験を積む必要が有るでしょう。しかしながら、ユーザーの特質次第では世間一般に提唱されている様々な手法が、必ずしもそのお客様にマッチする方法論であるとは限りません。 本講座では要求開発方法論に限らず、他のどのような方法論でも必要なテクニックであり重要な要素である「ステークホルダー分析」「問題分析」「要求分析」にスコープし、それらのテクニックを学んでいただきます。これらのテクニックだけでも身に付けることで、ユーザーの気付いていない価値の提案、そして確かな合意形成につなげていくことが可能になります。 1.要求開発の概要解説 -要求開発の位置付け、要求開発プロセス 2.要求開発方法論(Openthology1.0)の解説 -プロセスの全体像 -プロジェクトステークホルダーの選定(演習有り) -分析テクニックと意識の向け方 -問題分析-ボトムアップ分析(演習有り) -要求分析-トップダウン分析(演習有り) 3.まとめ -要求開発の目的と効果、活用方法 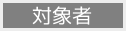 -超上流工程のテクニックを身に着けたい方 -情報システム部門などで自社のIT活用を検討したい方 -ユーザー要望のとりまとめ方法を身に着けたい方 -要件定義フェーズでのテクニックを知りたいITエンジニア  -システムライフサイクルの一般的知識 -UMLの初歩的な知識 ※いずれも必須ではございません  6名~16名 ※6名未満、または16名超で実施をご希望の場合はご相談ください。  6名~16名様の場合、¥400,000(弊社開催オンサイトの場合) ※上記人数の範囲外の場合はご相談ください。 ※他社での開催の場合料金が異なります。詳しくは各企業のサイトにてご確認ください。  公開講座の場合は指定の会場。オンサイトの場合は受講企業様にてご準備いただきます。 会場に必要な什器・機材についてはご相談ください。 ★過去の参加者の声★ !具体例を挟みながら進行していて、内容を上手く落とし込みやすかった。 !ITベンダーとお客様で責任の切り分けで壁を作るという話が思い当たるふしがあって改善しようと思う事ができた。 !視覚的に分かりやすいパワポの資料の下に細かい解説がついており、見直しがしやすい。 |
|
GKI社:応談 一社研修:応談 IT-X:2025年度終了 1日(6.5~7.0H) |
若手プログラマー向け 【成長力】を加速させるマインド研修 ★特に人気です! |
新人~3年目程度までの若手プログラマーを対象に、プログラマーがシステム開発現場において持つべき思考と、思考の整理方法を学習します。
本コースでは「要求開発方法論」のエッセンスを採り入れており、単なる意識改革セミナーとは一線を画します。要求開発の神髄とも言える「モデリングによる見える化」、そして「目的と手段のトレーサビリティ」「問題の論理構造分析」などのテクニック、そしてそれらのテクニックを用いる際に必要になる「マインド」を、演習を通じて学習することができます。
これらのマインド学習は、若い内に習得することで、その後のビジネスマン・ITエンジニアとしての成長力を増幅させます。 本講座は若手プログラマーを対象に開発しておりますので、新人フォローアップ研修としてもご活用いただけます。 1.プログラマーの仕事とは? -一般論で語られるプログラマーの仕事を振り返り、深堀することにより、プログラマーの仕事の本質を学びます 2.プログラマーが現場で持つべき思考 -【優秀な】プログラマーが現場でどのような思考・マインドをもって業務に取り組んでいるのかを学びます 3.思考の整理方法 -思考を整理する方法としてロジックツリー(Whyツリー、Howツリー)を学びます -ロジカルに考える上で重要な思考方法である「Howの手探り」「Howからの突き上げ」「Howのチューニング」を学びます 4.実践演習 -2~3章で学んだ思考・マインド・整理方法を活用した演習を行うことで、学習内容を身に付けます 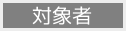 -1~3年目程度の若手プログラマー -お客様やチームから評価されたいと考えている方 -現場にいる「スゴい人」に近づきたい方  -成長したいと言う想いだけで十分です  6名~16名 ※6名未満、または16名超で実施をご希望の場合はご相談ください。  6名~16名様の場合、¥350,000(弊社開催オンサイトの場合) ※上記人数の範囲外の場合はご相談ください。 ※他社での開催の場合料金が異なります。詳しくは各企業のサイトにてご確認ください。  公開講座の場合は指定の会場。オンサイトの場合は受講企業様にてご準備いただきます。 会場に必要な什器・機材についてはご相談ください。 ★過去の参加者の声★ !光る社員になりたいと思った。手段を多く探すコツを知りたいと思った。 !今回学ばせていただいた論理的思考は開発だけではなく様々な状況で活用できる。 !今日研修を受けることができて良かったです。来週から意識を変えて仕事に取り組んでいこうと思います。 |
|
GKI社:応談 一社研修:応談 IT-X:2025年度終了 1日(6.5~7.0H) |
新入社員向け ITエンジニアになるためのマインド研修 |
”ITの学習は未経験だが、ITエンジニア職で採用された。まず何を学べば良いのだろう?” ”プログラミングは学生時代に学んできたが、いざITエンジニアとしてやっていくために必要なことは何だろう?” 新卒採用された新人たち、あるいは採用活動中の学生たちと会話すると、このような疑問を良く投げかけられます。 ITエンジニアに求められる能力とはどのような能力でしょうか? 例えばプログラミングやデータベースなどの技術的知識は当然必要でしょう。しかしながら、それらの技術要素はITエンジニアにとっては【道具】の一つにすぎません。
エンジニア=技術者として道具を適切に・正しく活用できるのは言うまでもありません。そのために技術的研修を受けることはとても大切でしょう。
しかし、ITエンジニアはそれだけで良いのでしょうか? ITエンジニアは、ただ単にIT技術を道具としてモノを作ればいい、と言うわけではありません。それだけなら、ITが進歩し市民権を得た昨今、自動でモノを生成するツールも有れば、ツール類を駆使して非ITエンジニアの人物が日曜大工で何かを生み出してしまうことも珍しくありません。 では何が大切なのか? ITエンジニアは【プロ】の技術者です。プロである以上、ITと言うものに対して責任を持ちます。そして単にモノを作るだけならばアマチュアでもできる世の中ですが、プロはさらにその先を求められます。 プロに求められるもの、それは【価値】です。ITエンジニアと言うITのプロは、IT技術を駆使して【価値を生み出す】ことが大切です。 ITによって価値を生み出し、その価値が開発者⇒サービス提供者⇒ユーザーと様々なステークホルダー(利害関係者)を巡っていく過程で、各ステークホルダーはその立場なりの価値を感じます。 ITのプロであるならば、自分たちが提供するITにより、「どのような価値が生まれ」「誰が」「どのように価値を享受するのか」を説明できる必要が有ります(説明責任)。 ITエンジニアを目指す、それはすなわち「ITに対する説明責任」を持ち、「ITによりステークホルダーに価値を提供する」ことを目指すこと、とも言えます。 本講座では、これから初めてITエンジニアの世界に飛び込む人物や、社会人1年目のIT企業の新人向けに構成された、ITエンジニアになるために必要なマインドを醸成する講座です。物事の捉え方や意識の向け方、考えを整理する力などを養うことを目的としております。 新人研修の一環として、あるいは新たにITエンジニアを目指す方にご活用いただける講座となっております。是非、ご検討ください。 1.エンジニアに必要な素養 -”エンジニアリング”とは何か? -誰のためのエンジニアリングなのか? -ITのプロとはどういうことか? 2.物事の捉え方 -エンジニアリングに必要な物事の捉え方=メカニズムの捉え方、視点の活用などについて学びます 3.手段は「考えて」「創り出す」 -安直に物事を考えない、プロのエンジニアであれば自らの答えを導き出す際のプロセスと裏付けが重要であることを学びます 4.エンジニアは三現主義であれ -様々なエンジニアリングの世界で活用されている考え方「三現主義」を学びます 5.まとめ、振り返り -全体の振り返りとまとめを行います 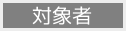 -新人のITエンジニア -別業種からITエンジニア職に転職した一年目の方 -漠然とシステム開発現場で仕事している若手エンジニア  -”プロのエンジニア”を目指す気持ち  6名~16名 ※6名未満、または16名超で実施をご希望の場合はご相談ください。  6名~16名様の場合、¥350,000(弊社開催オンサイトの場合) ※上記人数の範囲外の場合はご相談ください。 ※他社での開催の場合料金が異なります。詳しくは各企業のサイトにてご確認ください。  公開講座の場合は指定の会場。オンサイトの場合は受講企業様にてご準備いただきます。 会場に必要な什器・機材についてはご相談ください。 |
|
GKI社:応談 一社研修:応談 IT-X:2025年度終了 1日(6.5~7.0H) |
”豊かさ”を創り出す 要求分析テクニック |
現在、ITテクノロジーは様々な分野で利用されております。それは、ビジネスシーンにおいても社会インフラなど、およそ人間が活動する全ての分野において同じことが言えます。 さて"DX"(デジタルトランスフォーメーション)と言われて久しい昨今ですが、本当の意味でDXを推進できている企業はどれだけあるのでしょうか? また、"DX"を推進してはいるものの、効果を実感できている企業・組織はどれだけあるのでしょうか?
"DX"は、進化し続けるテクノロジーが人々の生活を豊かにしていく、と言う概念です。従って、ただ闇雲にIT活用を推進したり、IT化を目指しているだけでは、それは"DX"とは言えません。
・テクノロジーが進化して ・人々の生活が豊かになる "DX"と言うからには、上記2点が満たされる必要が有ります。言い換えると、人々の生活を豊かにするため、進化し続けるITテクノロジーが必要になります。(もちろん、テクノロジーはITだけではありませんが、本講座ではITテクノロジーに着眼します) ではそのようなITテクノロジーとは、いったいどのような物でしょうか? 答えはそこに落ちているようなものではありません。誰かが答えを持っている訳でもありません。もちろん、ネットで検索しても答えは出てきません。(成功事例"だけ"はたくさん出てくるかも知れませんね) 「豊かになろう」、あるいは「豊かにしたい」と考えている、そこを目指している人々が答えを創り出すべきものです。 IT活用やDX推進が叫ばれる昨今、IT技術を企業のIT活用推進やDX推進に活用できるDX推進担当者が求められています。システム開発者も技術を追い求めるだけでは、これからの時代のIT業界で生き残ることは困難です。 本講座では超上流工程のメソッドの一つである「要求開発方法論(Openthology1.0)」を用いて、IT活用やDXを推進するためのやり方や着眼点、持つべき意識を学びます。本講座で学んだことを、みなさまの所属企業や顧客企業のIT活用・DX推進に役立たせてください。 1.求められるIT活用とDX -今の時代に求められているIT活用やDXの姿、要求開発方法論との関連について学びます 2.要求開発とは -要求開発方法論の生まれた背景や必要性について学びます 3.要求開発方法論~導入プロセス~ -要求開発プロセスの導入部分、マインドの持ち方、ステークホルダー分析、分析テクニック、価値のデザインについて学びます 4.要求開発方法論~分析プロセス~ -問題分析と課題の定義、戦略の見える化、要求分析と要求定義を学びます -AsIs分析とToBe分析を学びます 5.まとめ、振り返り -全体の振り返りとまとめを行います 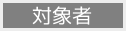 -超上流工程のテクニックを身に着けたい方 -情報システム部門などで自社のIT活用を検討したい方 -DX推進したいがそのやり方が解らない方  -システムライフサイクルの一般的知識 -UMLの初歩的な知識 ※いずれも必須ではございません  6名~16名 ※6名未満、または16名超で実施をご希望の場合はご相談ください。  6名~16名様の場合、¥450,000(弊社開催オンサイトの場合) ※上記人数の範囲外の場合はご相談ください。 ※他社での開催の場合料金が異なります。詳しくは各企業のサイトにてご確認ください。  公開講座の場合は指定の会場。オンサイトの場合は受講企業様にてご準備いただきます。 会場に必要な什器・機材についてはご相談ください。 ★過去の参加者の声★ !要求は、存在するものではなく、開発するものであるという言葉が印象に残りました。営業として新しい視点が身に付くきっかけになりました。ありがとうございました。 !DX化を図るために、お客様のニーズ、課題、現状をヒアリングし、見える化、要求、分析を行い、解決策を提案することを意識していきます。 |
■NDS要求開発研修シリーズ 匠Method + 若手エンジニア向けコアスキル研修
NDSと匠BusinessPlace社のコラボレーションで生まれた、一社開催向け研修コースです。管理者・リーダー・次世代リーダーに向けた匠Method研修は、ビジネスの未来を描きながら、DXに不可欠なマインドチェンジと思考力を養う、他に類を見ない革新的なビジネス企画手法を学びます。
若手エンジニア向けコアスキル研修では、将来のリーダーとなるべく若手エンジニア向けに、匠Methodの根底とも言える匠Thinkの言葉を用いて、ITの匠となるための思考・意識・マインドを学びます。
これまでの階層別研修では、様々な研修ベンダーが提供している数多くある研修の中から、それぞれのレイヤに合った研修を探し当てて受講しており、ともすると違う思想の研修を受講してしまうケースも有りました。
この研修コースは、レイヤ毎に違った研修では有りますが、根底の思想は全く同じところから生まれており、一社の中でのリーダー層、若手層、それぞれのレイヤに合った研修を受講することで、適切なレベル感の講座を受講したうえで、共通の想い、共通の言語で同じ未来を目指すことが可能になります。
企業内で違うレイヤの社員に対して、別々の思想の研修を行うことは、企業の未来を見据えたときにナンセンスとも言えます。
本研修コースを受講することで、若手・中堅・ベテランそれぞれが同じ思想を持ち、同じ未来を描くための礎を築き上げることができます。
なお、本研修コースはセットで受講することが望ましいですが、どちらか片方の受講も可能です。
また、内容のカスタマイズにも応じることが可能ですので、ご要望が有ればお問い合わせページより、弊社担当者までお問い合わせください。

原則、貴社オンサイトにて行います。貴社にて会場準備が難しい場合はご相談ください。
会場に必要な什器・機材については以下の通りです。準備が難しい場合はご相談ください。
- プロジェクター等の資料投影機材
- ホワイトボード(講師用)
- 模造紙+付箋+マジックやサインペン、またはホワイトボードツール(Miroなど)
研修パンフレットはこちらからダウンロードしてください。
▼シリーズ1 匠Methodビジネスデザイン入門研修コース
本研修では、DXに必要不可欠な「価値から考える」思考法と、その可視化手法を1日で集中的に学びます。前半は、匠Method開発者・萩本順三による講義にて、ビジネスデザインの本質と図式化の技術を習得。
後半は、チームワーク形式で実際のビジネスケースをもとに匠Methodの各モデルを作成しながら、価値創造のプロセスを体験的に学んでいただきます。
参加者は、ビジネスの設計と価値創造のプロセスを体験的に学び、ビジネスデザインのスキルの基礎を習得します。
- DXビジネスに通用するリーダーを育成する
- 様々な企画に使える匠Methodの手法としての基本を理解し、社内で活用できるようになる
- 匠Methodの価値から考える思考法を身に付け、普段から価値から考えることを身に付ける
- 既存のプロジェクトで匠Methodのモデル図を活用できるようになる
-
1.匠Method入門(講義形式1時間)
匠MethodによるDXビジネスデザインの必要性、思考法、モデル(図式化)ベースで見える化する方法を講師よりお伝えします。 -
2.ビジネス検討
当日の参加者でビジネステーマを決めたい時は、この時間内でコース推薦例や自社例にて決めていただきます。 -
3.ステークホルダーモデルの作成(ワーク)
ビジネスになくてはならないステークホルダーを検討・発見し、図式化します。 -
4.価値分析モデルの作成(ワーク)
「3.ステークホルダーモデル」でまとめたステークホルダーモデルを基に、ステークホルダーの未来の価値をストーリーとしてまとめて図式化します。 -
5.価値デザインんモデルの作成(ワーク)
自チームの意志をビジョン・コンセプト・言葉・デザインなどの表現で明確な言葉の構造として図式化します。 -
6.要求分析ツリーの作成(ワーク)
「4.価値分析モデル」と「5.価値デザインモデル」の要素を結合して、自チームが行うべき要求を作成します。要求の要素は戦略要求・業務要求・IT要求(ITが関係する場合)となります。
要求を満たすための活動を発見します。 -
7.発表とレビュー・振り返り
チーム毎に、作成したモデルを発表し、講師から作成内容についてレビュー及びディスカッションを行います。
※講義アジェンダはご要望に応じてカスタマイズ可能です
-
実践的なビジネスデザイン
仮想のビジネスケースや実際の事業課題を題材に、匠Methodの基本モデルを用いて、価値創造から戦略立案、そして活動計画までのプロセスを体験します。 -
思考のフレームワークを習得
匠Methodの体系的なフレームワークを通じて、チームでの創造的な対話を促進し、企画力・構想力を強化します。 -
「創り出す力」と「考え抜く力」を鍛える
単なる知識の習得ではなく、実際に“考えながら創る”プロセスを繰り返すことで、持続的に使える思考の型を身につけます。
-
三菱電機DXイノベーションセンターでの匠Method研修・共創サービス
三菱電機Serendie関連事業の推進組織として立ち上げられたDXイノベーションセンター(DIC)にて、新規ビジネスでビジネスデザイン研修、ビジネスプロダクト構想・企画実践サポートで採用されています。
-
富士通のビジネスプロデューサーに向けたDXビジネスデザイン研修
富士通のデジタル改革加速をテーマとした下記の研修で営業職1500名が匠Methodによるビジネスデザイン研修6回コースを受講されました。
https://japan.zdnet.com/article/35167291/
-
大和ハウスビジネスデザイン研修
大和ハウスのDXビジネスデザイン研修に採用され、DXアニュアルレポートに掲載されました。
https://www.daiwahouse.co.jp/ir/dxar/2021/organization/department/collective_intelligence.html
-
早稲田大学の社会人研修・スマートエスイー
早稲田大学の社会人研修・スマートエスイーに「DXプロジェクトデザイン研修」として毎年実施しております。
https://www.waseda.jp/inst/smartse/subject/1184
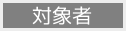
- DX推進を担う企画担当者・マネージャー
- 新規事業・サービス開発を担うリーダー・チームメンバー
- 組織変革を進める部門のメンバー
- ビジネス設計・価値創造に関心のあるビジネスパーソン全般

4名~20名
※4名未満、または20名超で実施をご希望の場合はご相談ください。

4名~20名様の場合、¥700,000
※上記人数の範囲外の場合はご相談ください。
ニッポンダイナミックシステムズ フェロー
萩本 順三

経理マンから27歳で転職、新米エンジニアとしてIT業界に飛び込む。
独学でソフトウェア工学を学び、開発作業に活かしているうちに自分でも開発手法が作れるのでないか?という考えに行きつき、1995年よりオブジェクト指向方法論を生み出し、IT業界に広く展開する。
2000年に、株式会社豆蔵を開発仲間と共に設立し、経営者となる。経営経験を活かし、ビジネスシステム開発手法(要求開発手法)の初版を作成した。
2008年に現在の会社を設立し、ビジネスや組織デザインにも活用可能な手法として匠Methodを開発し、継続的に進化させている。
現在は、コンサルティング・研修において匠Methodの活用を企業で指導している。
また、未来に向けて、新しい価値観で社会やビジネスを創造できる人材を育てたいという想いから、慶應義塾大学大学院SDM研究科(2014~2018)や、早稲田大学理工学術院(2016~2023)、東大大学院(2023年~現在)の授業で匠Methodによるビジネスデザインを教えている。
-
2022年 日本ビジネスアナリシス賞受賞(IIBA Japan)
匠Methodを活用したソーシャルデザイン事例等を2019年,2022年の2回、フロリダにて開催されたIIBA主催のBABOKイベントにて講演した内容が評価された。
主な著書
- ビジネス価値を創造する匠Method活用法 翔泳社
- 匠Method、アマゾン、萩本順三
- 要求開発 日経BP 共著
▼シリーズ2 若手エンジニア向けコアスキル研修コース
DXを推し進めるDX人材として、価値を創造する力の習得と、それをステークホルダーの間で共通認識とするスキルは欠かせません。そのやり方の1つとして要求開発方法論、さらには進化系である匠Methodが存在します。
これらを習得するにはそれなりの経験値が必要になりますが、単に経験を積んだだけでは習得できません。その最も底辺を支えているコアスキルである、想いや気持ち、姿勢、目線、意識、マインドの醸成が不可欠になります。
本研修では、将来のDX人材の礎となるコアスキルを、「現場で優秀と評される人たち」の特徴から学んでいきます。これらを学ぶことで「優秀な人材」へ成長する速度を加速させていくことができます。
- 将来のDX人材や、組織・ビジネスをリードする人材を育成する
- 現場で「優秀」と評されるような若手人材を育成する
- 若手社員に対して、「シリーズ1 匠Methodビジネスデザイン入門研修コース」を受講する中堅~ベテラン社員と想いや言葉、意識の持ち方を合わせたい
-
1.プログラマーの仕事とは
一般論で語られるプログラマーの仕事を振り返り、深堀することにより、プログラマーの仕事の本質を学びます -
2.プログラマーが現場で持つべき思考
【優秀な】プログラマーが現場でどのような思考・マインドをもって業務に取り組んでいるのかを、匠Thinkの言葉を用いて学びます -
3.思考の整理方法
思考を整理する方法としてロジックツリー(Whyツリー、Howツリー)を学びます
-
4.実践演習(ワーク)
2~3章で学んだ思考・マインド・整理方法を活用した演習を行うことで、学習内容を身に付けます
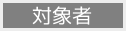
-1~3年目の若手ITエンジニア
-将来的にDX人材、DX推進リーダーを目指す方
-現場にいる「スゴイ人」を目指したい方

4名~20名
※4名未満、または20名超で実施をご希望の場合はご相談ください。

4名~20名様の場合、¥350,000
※上記人数の範囲外の場合はご相談ください。
■e-ラーニング(Udemy提供)
弊社教育コンテンツをUdemyでご提供いたします。Udemyはマイクロラーニングが主体です。動画は1~10分程度に収められており、受講者のスキマ時間で受講いただけます。
お得な割引クーポンを利用できるケースもございますので、是非ご活用ください!
| 講座タイトル | 動画時間目安 | 通常価格 | ご提供方式 | コース内容 |
|---|---|---|---|---|
| ”豊かさ”を創り出す 要求分析テクニック[Udemy版] | 約193分 | 19,800円 | Udemy |
こちらはUdemyでの配信講座になります。
内容は公開講座の「”豊かさ”を創り出す 要求分析テクニック」と同様です。 Udemy版はマイクロラーニング化されており、全7セクション、動画数22本で構成されております。1動画10:00前後程度で構成されているため、スキマ時間を利用して学ぶことが可能です。 お得なクーポンによる割引が使えるケースもございますので、是非ご活用ください。 ※クーポンは数に限りが有ります。 |
| 若手プログラマー向け 【成長力】を加速させるコアスキル研修[Udemy版] | 約150分 | 17,800円 | Udemy |
こちらはUdemyでの配信講座になります。
内容は公開講座の「若手プログラマー向け 【成長力】を加速させるマインド研修」と同様です。 Udemy版はマイクロラーニング化されており、全9セクション、動画数33本で構成されております。1動画1:30~10:00程度で構成されているため、スキマ時間を利用して学ぶことが可能です。 お得なクーポンによる割引が使えるケースもございますので、是非ご活用ください。 ※クーポンは数に限りが有ります。 |
| 新人向け ITエンジニアコアスキル研修[Udemy版] | 約117分 | 15,000円 | Udemy |
こちらはUdemyでの配信講座になります。
内容は公開講座の「新入社員向け ITエンジニアになるためのコアスキル研修」と同様です。 Udemy版はマイクロラーニング化されており、全7セクション、動画数27本で構成されております。1動画2:20~7:30程度で構成されているため、スキマ時間を利用して学ぶことが可能です。 お得なクーポンによる割引が使えるケースもございますので、是非ご活用ください。 ※クーポンは数に限りが有ります。 |
■e-ラーニング(Videoダウンロード提供)
弊社教育コンテンツをe-ラーニング形式でご提供いたします。講座の各パートは20~30分程度に収められており、受講者のご都合に合わせて自由なタイミングで受講いただけます。
e-ラーニングご購入をご希望の方は、お問い合わせページより、弊社担当者までお問い合わせください。
| 講座タイトル | 所要時間目安 | 価格 | ご提供方式 | コース内容 |
|---|---|---|---|---|
|
若手プログラマー向け 【成長力】を加速させるマインド研修 |
約310分 | 80,000円 | ダウンロード形式 |
2016年の初開催以来、弊社教育講座で最も人気の高い講座をe-ラーニング化しました!
公開講座の「若手プログラマー向け 【成長力】を加速させるマインド研修」のe-ラーニング版です。全8編の動画で構成されており、短いもので10分程度、長いものでも35分程度ですので、ご受講者様のご都合に合わせて受講できます。 公開講座と異なる点として、講師の経験談や現場のリアルな話等は除外されておりますが、その分各項目を丁寧に解説しております。 公開講座を受講したいがタイミングが合わない方や、開催地の都合で受講が難しい場合にご活用ください。 |
要求開発の啓蒙および教育のため、お客様の拠点にて目的やニーズに応じカスタマイズした内容で教育研修を行います。
メーカー系SI企業、独立系ソフトハウス、インターネットサービスプロバイダなど、様々なIT企業でニーズに合ったコース体系にカスタマイズして実施しております。
■過去のオンサイト教育実施例
| 受講者企業 | 受講者のオーダー | 実施内容 |
|---|---|---|
| 独立系ソフトベンダー | 主力製品のパッケージビジネスが成功したが、近年入社の社員は開発時の苦労を知らず、このままでは近い将来、苦労を知っている社員が減り、苦労を知らない社員が主力になっていく。その状態でこの業界を生き抜いていくのは難しいと考えている。そこで、若手社員や近年入社した社員を対象にマインドを含めて超上流のプロセスを学習させ、意識改革を行いたい。 |
実施期間:二日間 若手チームと中堅以上チームに分かれ、それぞれ別のテーマに基づいて二日間の教育を実施。一日目は要求開発方法論の概要を中心に座学形式で実施。二日目は例題(パッケージバージョンアップ案件)を用いて、実際に要求開発を行う実践演習。例題は受講者企業の担当者と相談し、オリジナルの例題を作成した。 ※一年後に同一メンバーにて、マインド面を中心に再度実施。 |
| 大手メーカー系SIベンダー | 大手メーカー系ではあるが、地方都市が拠点と言うことも有り、その実多くの案件は東京本社の下請けと言うイメージが強い。社員もそれが当たり前のような感覚に陥っており、自分たちの強みなどをビジネスに活かせていない。悪く言えば「上に言われたことをそのままやっている」状態となっている。企業として危機感を感じるので、社員のモチベーション向上を期待して、実践的な内容を受講したい。 |
実施期間:二日間 中堅~ベテランのエンジニア、および営業職が参加。初日は要求開発方法論の概要と基礎を座学形式(一部演習有り)で学習。二日目は実際に存在するユーザー企業の例をカスタマイズした例題を用いて、システムの提案~システム要求の策定までを、要求開発方法論に基づいて実践演習として実施した。 |
| 独立系ソフトハウス | 要求開発方法論の基礎教育は実施済みの企業。SES主体のビジネスだが、このままでは社員のモチベーションも上がらず、またスキル価値が認められず、月額単金の向上・売上向上に繋がっていかない。社員に提案する能力を身に付けさせ、ビジネスの発展につなげたい。 |
実施期間:5ヶ月 SESで現場に出ているエンジニア6名で実施。それぞれの現場における問題や課題、達成目標をインプットとして、1回/月の会合とオンラインでのQAをベースに、5ヶ月かけて問題分析や要求分析を行った。実際の現場課題などを元ネタとしているので、教育と言うよりもコンサルティングに近い形で実施。通常、このような超上流の方法論は、よりユーザーに近い立ち位置、あるいはユーザー自身が実施することが前提と思われているが、もっと別の立ち位置・目線でも適用して意味のあることを体験した。 |
| 大手インターネットサービス | 様々なインターネットサービスを手掛けており、ここ数年で多くの部署が乱立、それに伴いシステムも乱立し、横の連携が取り難い状況となって整理が必要な状況になってきている。今一度、自分たちのあるべき姿を見つけ出す方法を模索しており、要求開発方法論もその一つとして学習したい。単なる学習ではなく、実際の課題や達成目標を元ネタとして実施することで、より臨場感を出していきたい。 |
実施期間:3ヶ月 全5チームに分かれて、1回/2週のペースで実施。各チームの抱える課題や達成目標をインプットとして、要求開発方法論の準備フェーズを中心に実施した。既に様々なやり方を実施した経験のある企業ではあるが、色々なアプローチの一つとして学習していただけた。規模感も大きく先進的な事業を行っている企業であるがゆえに途中の分析過程では、やや迷走するチームも有ったが、最終的には目指す方向性を見える化することに成功した。 |
■その他、講演・セッション、コラム執筆等のご依頼について
社内の勉強会やミニセミナー等でのショートセッション(30分~90分程度)や、コラム執筆等のご依頼も受け付けております要求開発方法論はもちろん、これまでに講師が経験した様々な開発プロジェクトやビジネス企画の経験をもとに、ビジネス企画・起ち上げやプロジェクト推進の勘所、効果的なIT活用のポイント。そしてそれを推進するためのマインドセットなどを解説します。
ご依頼内容に合わせて、講演のみの他、ワークショップを実施することも可能です。
講演・セッションについてのご相談は、お問い合わせページより、弊社担当者までお問い合わせください。
▼過去の事例
大手光学機器メーカー社内セミナー ~要求開発方法論と効果的な活用方法について~
SIベンダー社内ミニセミナー ~BABOKの活用方法~
IT系交流会ミニセミナー ~要求開発の良いところ3選!~
IT系インターネットメディア(記事執筆) ~要求開発の使いどころ・勘どころ~
独立系ソフトハウス社内勉強会 ~要件定義のポイントと大切なマインド~
■講師略歴
イノベーションディレクター
浅利 智英 (Tomohide Asari)
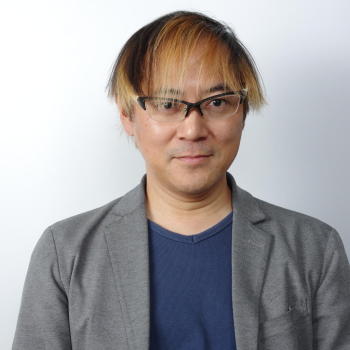
1974年生まれ。
中堅ソフトウェアハウスにて組込制御開発から始まり、公共システムや基幹系システムなど幅広いジャンルのシステム開発に携わる。
黎明期よりJavaによるシステム開発に携わり、各種普及活動にも参加。
その後、IT系ベンチャー企業の起ち上げに参加する傍ら、同社にて技術責任者や新ビジネスの企画・推進を牽引。
以降、いくつかのシステム開発会社にて開発リーダーやプロジェクトマネージャ、部門マネージャを担当。
2012年に現在の(株)ニッポンダイナミックシステムズに入社し、複数のシステム開発プロジェクトで技術アドバイザーを兼務しつつ、要求開発を活用したコンサルティング業務や教育講師、シンポジウム等でのセッションプレゼンターを担当している。
- 第25回 iSUC札幌大会 優秀講師賞【BRONZE】受賞
- 第53回 IBMユーザー論文【銀賞】受賞
▼主なセッション登壇
- (一社)情報サービス産業協会 SPES2013
- IBMユーザー研究会 iSUC(第24回~第28回)
- User&IBM NEXT2019
- 日本プロジェクトマネジメント協会 九州P2Mセミナー 招待講演