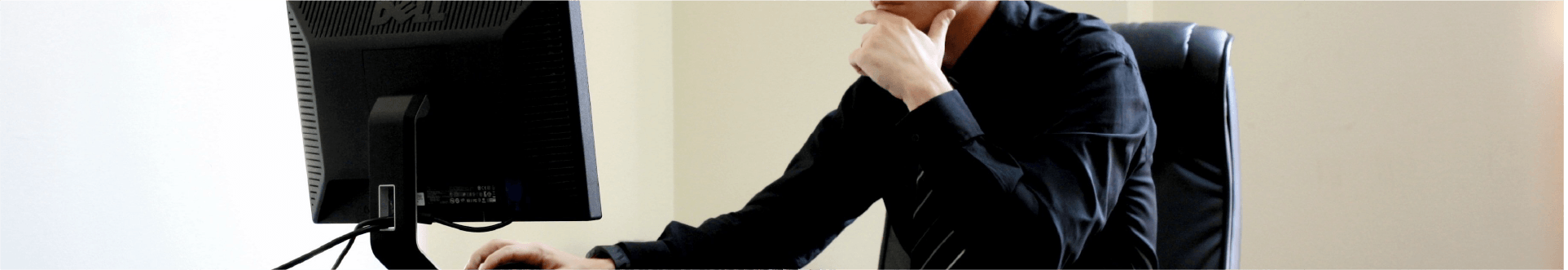 企業リスクを未然に防ぐ労務監査とは?
企業リスクを未然に防ぐ労務監査とは?

企業を経営する上で、法律を遵守し、従業員が安心して働ける環境を整えることは不可欠です。しかし、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令は頻繁に改正され、そのすべてを正確に把握し、適切な労務管理を行うことは容易ではありません。
そこで重要となるのが労務監査です。そこでこの記事では、労務監査の具体的な目的や重要性、実施するタイミング、主要なチェック項目、そして監査でよく指摘される事項について詳しく解説します。労務監査によって、企業の信頼性とブランド価値を向上させる方法を理解し、より盤石な経営基盤を築きましょう。

労務監査は、企業が労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令を遵守し、適切な労務管理を行っているかを精査する重要なプロセスです。ここでは、労務監査に関する基礎的なことを以下の4つのポイントから解説します。
●労務監査の目的
●労務監査の重要性と避けたいリスク
●労務監査が企業にもたらすメリット
●労務監査を実施するタイミング
労務監査は、企業が労働関係法令を遵守しているか、また適切な労務管理が行われているかを専門的な視点から精査するのが目的です。単に法令遵守をチェックするだけでなく、未払い残業代や社会保険の未加入といった「簿外債務」のリスクを洗い出してくれます。また、企業の財務健全性を高める上でも重要な役割を担います。特に、株式公開(IPO)や企業買収(M&A)を検討する企業にとっては、企業の信頼性とブランド価値向上にも役立ちます。
企業経営において、避けたいリスクとして以下のようなものがあります。
●労働基準監督署による行政指導や罰則
●従業員との間の訴訟リスク
●SNSなどでの情報拡散による企業イメージの著しい低下
中小企業では、労務管理に関する専門知識を持つ担当者が不足していることが多く、意図せず法令違反を犯してしまう可能性も少なくありません。ブラック企業と認定されてしまうと、採用や従業員の定着率にも大きく影響を及ぼします。
労務監査は、企業コンプライアンスの強化だけでなく、以下のようなメリットをもたらします。
●法律違反の未然防止
●労働環境の整備と生産性向上
●企業のブランド価値向上
労働基準法や雇用保険法などの労働関係法令への対応状況を詳細に確認できます。結果を受けて、適切な労務管理体制へと改善されると、従業員の満足度向上や離職率の低下、業務効率向上へとつながるでしょう。株式公開(IPO)や企業買収(M&A)の際にも、労務管理の健全性が評価に影響を及ぼします。
労務監査を実施する代表的なタイミングとして3つ紹介します。
1.新規上場株式(IPO)を準備する段階
上場審査では、法令違反がないことが厳しくチェックされます。労務監査で事前にリスクを洗い出し、対策を講じておくと、審査をスムーズに進められるでしょう。
2.スタートアップ企業が急成長しているタイミング
従業員が急増する成長期は、労務管理が追い付かず、トラブルが発生しやすくなります。このタイミングで労務監査を実施すれば、今後起こりうるリスクを未然に防げるでしょう。
3.一度も労務監査を実施していない企業
労務管理に少しでも不安を感じたら、労務監査を実施する絶好の機会です。専門家の視点で現状を把握し、健全な経営基盤を築きましょう。

労務監査では、企業の労務管理体制が多角的にチェックされます。ここでは、重要となる以下の主要項目について詳しく解説します。
●就業規則・雇用契約の適正化
●労働時間・残業時間管理の徹底
●ハラスメント・安全衛生・健康管理体制
●社会保険・労働保険の適性加入
●育児介護休暇・個人情報管理など
就業規則は、労働時間や賃金、退職に関する事項などを定めた企業の基本的なルールブックです。常時10人以上の社員を使用する事業場では、作成と労働基準監督署への届け出が義務付けられています。10人未満の企業でも、労務トラブルを未然に防ぐため作成が強く推奨されます。
労務監査では、以下のような点が確認されます。
●絶対的必要記載事項の網羅性
●相対的必要記載事項の記載
●法改正への対応
●雇用形態別のルール
就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」には、労働時間、休憩、休日・休暇、賃金の決定・計算・支払い方法、退職に関する事項などがあります。企業が制度を設ける際の「相対的必要記載事項」は、退職手当、賞与、安全衛生などです。
正社員と有期雇用社員で就業規則や待遇が異なる場合、それぞれで適切に作成・周知されているかを確認しましょう。労働法は常に変化しているため、就業規則が最新の法改正に適切に対応しているかも重要です。
法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて従業員に労働させる場合や、法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結と労働基準監督署への届出が必須です。
チェックされる事項として、以下のようなものがあります。
●36協定が適切に締結・届出されているか
●時間外労働の上限規制(原則月45時間、年360時間)が遵守されているか
●特別条項の適用が適切か
●労働者代表が会社側によって選任されていないか
監査では、単に36協定が届出されているかだけでなく、その運用実態まで細かくチェックされます。
参考サイト:厚生労働省|労働時間・休日
従業員が心身ともに健康に働ける環境を整えることは、企業の重要な責任です。ハラスメント対策や安全衛生管理体制を整えるために、以下のようなチェック項目があります。
●パワハラ、セクハラ、マタハラなどの防止措置が講じられているか
●相談窓口が設置され、従業員が安心して相談できる環境が整っているか
●定期的な従業員への研修が実施されているか
パワハラに対しては相談窓口の開設や定期的な研修が有効です。また、労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場では産業医の選任が義務付けられています。月80時間以上の時間外労働を行い、疲労蓄積が認められる従業員(管理監督者含む)に対しては、医師による面接指導を受けさせる義務があります。
社会保険や労働保険に関して以下の2点について確認されます。
●加入漏れの有無
●算定基礎の適正性
加入漏れは、パートタイマーや正社員といった雇用形態に関わらずチェックされます。加入漏れが発覚した場合、最大で過去2年間に遡って保険料を納付する義務が生じるので注意が必要です。パートタイマーやアルバイトなど、一定の基準を満たす従業員が適切に加入しているかを確認しましょう。
通勤手当や残業手当など、社会保険料の計算に含めるべき手当が適切に算入されているかも重要です。非正規雇用者に対する適用や、算定基礎となる手当の計算ミスは、監査や行政機関の調査によって顕在化するまで見過ごされがちなため注意しましょう。
労務監査では、育児休業・介護休業制度の整備状況と運用実態も確認されます。育児休業は原則子が1歳に達する日まで、介護休業は対象家族1人につき通算93日を上限に最大3回まで分割取得が可能です。
また、個人情報管理に関するチェック事項では、労働者名簿や賃金台帳などの法定帳簿が適切に作成され、原則5年間保管されているかといったものがあります。個人情報が適正に管理され、情報漏洩のリスクがないかなども確認しましょう。
さらに、フリーランスや業務委託契約者の雇用についても厳しくチェックされます。契約の名称に関わらず、実際の労働実態が雇用関係にあると判断された場合、企業は労働者として適用されるすべての労働法規(最低賃金、労働時間、社会保険など)の義務を負うことになります。
参考サイト:労働基準法第百九条:記録の保存
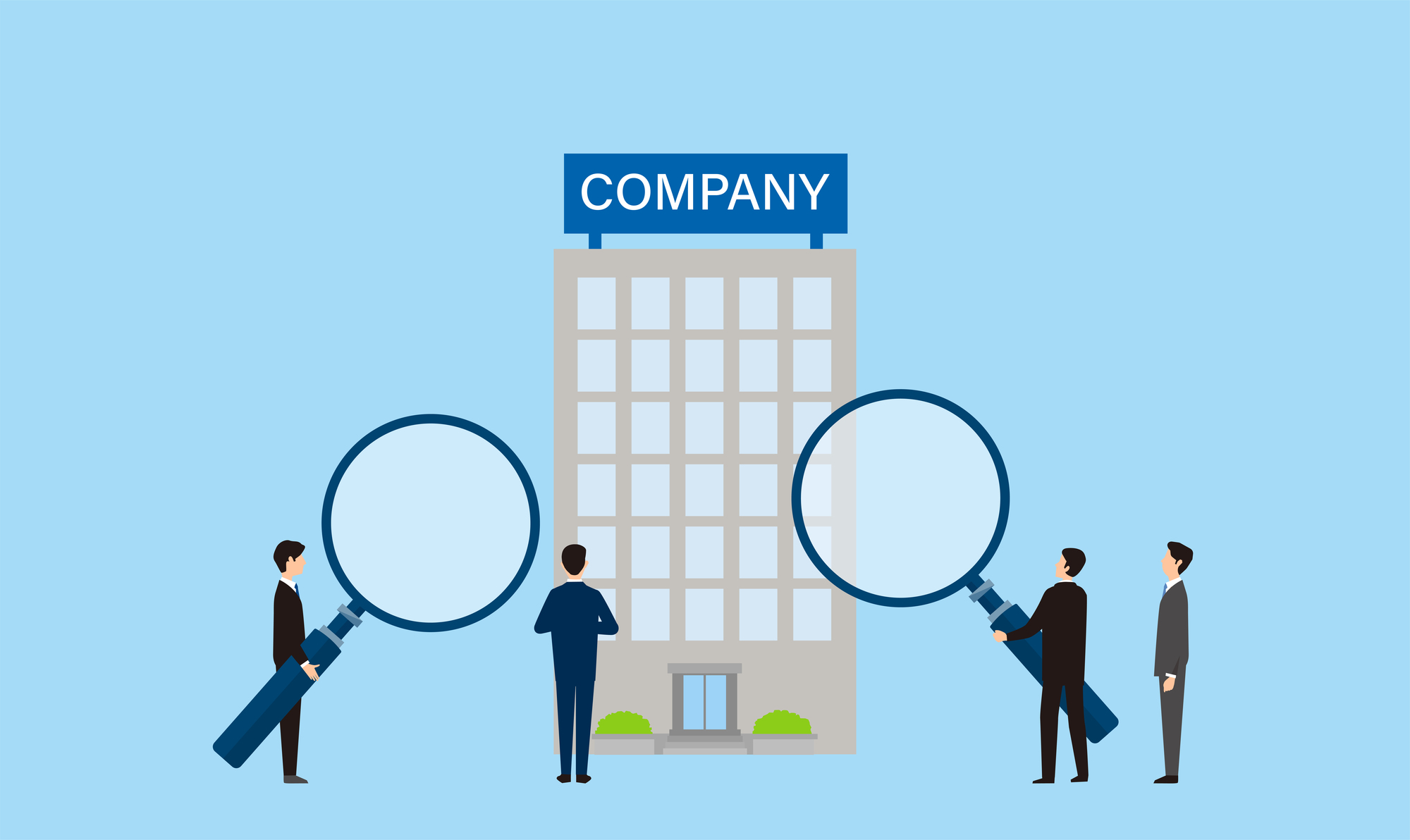
労務監査の一般的な流れと具体的な実施方法について、以下の3ステップで解説します。
1.実施準備
2.監査実施
3.監査報告と改善案の検討
監査業務に入る前に、進め方や方針を決定します。主に以下の項目を事前にすり合わせておきましょう。
| 決定すべき事項 | 詳細 |
|---|---|
| 監査の目的 | 株式公開準備、コンプライアンス強化、特定の労務トラブルの予防など、目的を明確にする |
| 対象とする範囲 | 全社、特定の部門、特定の雇用形態など、監査範囲を決定する |
| 監査の期間 | 監査にかかる期間を定める |
以上の項目を決定した後に、監査に必要な書類の確認と準備を行います。そろえるべき書類は、就業規則、雇用契約書、賃金台帳、勤怠記録、36協定、労働者名簿、健康診断結果などです。書面監査のベースとなるため、どの書類も正確に準備する必要があります。
監査は、書類・ヒアリング・視察など多角的に行なわれます。書面監査では、事前に準備された書類を詳細に確認し、労働法規や社内規程との整合性を検証します。従業員へのヒアリングでは、経営陣や人事担当者だけでなく、一般従業員に対しても行われます。労働環境や労働条件に関する聞き取りは、書面だけでは見えてこない実態や潜在的な問題点を把握できます。ヒアリングの方法は、直接インタビューする以外にアンケート調査も有効です。職場環境の安全性や衛生状態、実際の業務フローなどの確認のために、現場視察という手段もあります。
監査の実施後、調査結果を詳細にまとめた「監査報告書」が作成され、経営陣や人事部門などの関係者に提出となります。報告書では、指摘された問題点と、それに対する具体的な改善策が提案されます。例えば、未払い残業代の清算方法、就業規則の改定、勤怠管理システムの再設定、ハラスメント防止研修の実施計画などです。
特に株式公開(IPO)を目指す企業は、指摘された項目について迅速かつ確実に改善措置を講じなければなりません。監査で明らかになったリスクに真摯に向き合い、改善を繰り返すことで、企業価値の向上に繋がります。

労務監査は、企業の隠れたリスクを明らかにする重要なプロセスです。ここでは、特に指摘されやすい問題点5つを具体的な内容とともに解説します。
●最も多いトラブル:残業代の未払い
●見落としがち:36協定の届出不備
●法改正に対応:就業規則の整備と周知
●偽装請負に注意:労働契約の不備
●客観的な記録が重要:労務時間管理の徹底
残業代の未払いは、労務監査で最も重点的に調査される問題です。未払い残業代が発覚した場合、企業は原則として過去3年間に遡って支払義務が生じます。従業員数によっては経営を圧迫するほどの「簿外債務」となり得るので注意しましょう。
残業代未払いの原因として、以下のようなケースが多く見られます。
●タイムカードの打刻時間と実際の業務終了時間が異なっている
●割増賃金の計算方法が間違っていた
●計算に含めるべき手当が漏れていた
●従業員が残業時間を適切に申告していない
●会社がサービス残業を黙認していた
これらのリスクを防ぐためには、PCログや勤怠管理システムなどの専門ツールを導入し、客観的な記録を残すことが不可欠です。
36協定とは、時間外労働や休日労働に関する労使協定のことです。以下のような不備がよく指摘されます。
●36協定が締結・届出されないまま、従業員が時間外労働や休日労働をしている
●協定で定められた時間外労働の上限時間(原則月45時間、年360時間)を超えて労働させている
●労働者代表が会社側によって不適切に選任されている
法定労働時間を超えて労働させる場合、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
参考サイト:厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」
就業規則は、企業の労務管理における基本中の基本です。しかし、以下の不備がよく見られます。
●常時10人以上の労働者を雇用しているにもかかわらず、就業規則を作成・届け出ていない
●労働時間や賃金などの「絶対的必要記載事項」や、退職金、賞与などの「相対的必要記載事項」が漏れている
●働き方改革関連法などの頻繁な法改正に対応できておらず、何年も見直しを行っていない
●作成された就業規則の内容が従業員に適切に周知されていない
就業規則は一度作成したら終わりではなく、継続的に見直し、法改正や企業の実態に合わせて更新していくことが重要です。
労働条件の明示は、労働契約締結時の企業の重要な義務です。最近では、業務委託契約の名称で契約を結んでいても、実態が雇用関係にある「偽装請負」が問題となっています。
監査では、契約書上の名称だけでなく、実際の労働実態が厳しくチェックされます。偽装請負と判断された場合、企業は当該業務委託契約者を労働者として扱わなければならず、過去に遡って残業代や社会保険料の支払義務が発生する可能性があるので注意しましょう。
労務管理の根幹をなすのが、労働時間の適切な把握です。客観的な記録がない場合、サービス残業や残業代未払いなどのトラブルが発生しやすくなります。労務監査では、この「客観的な記録」の有無が厳しく問われます。厚生労働省のガイドラインに従い、勤怠管理ツールやPCログなどを用いて、記録を残すようにしましょう。
参考サイト:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

多発する法改正や多様化する働き方に対応するため、企業は労務リスクへの対策を求められています。特に、未払い残業代や社会保険の加入漏れといったリスクは、企業の財務健全性を損なうだけでなく、社会的信用の失墜にもつながりかねません。
これらのリスクを可視化し、企業の安定性を高める上で重要なのが労務監査です。特に、株式公開(IPO)を目指す企業にとって、労務監査は経営基盤の強化と信用度向上に不可欠です。
労務監査で頻繁に指摘される「見えない残業」や「労働時間管理の不備」は、PCログを活用することで未然に防げます。また、PCログと勤怠管理データを照合すれば、サービス残業や隠れ残業の実態を把握でき、適切な対策を講じることも可能です。
ez-PCLoggerは、PCのログオン・ログオフ情報収集に特化したクラウドサービスです。低コストながら、在宅勤務やシェアオフィスなど、働く場所を選ばずに客観的な労働時間データ収集が可能です。これまで多くのIPO企業やスタートアップに導入されており、各種勤怠システムとの連携もスムーズです。
スタートアップ企業から大企業にも対応できる柔軟な設計で、貴社の労務管理を強力にサポートします。トライアル期間中は、無料でご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。