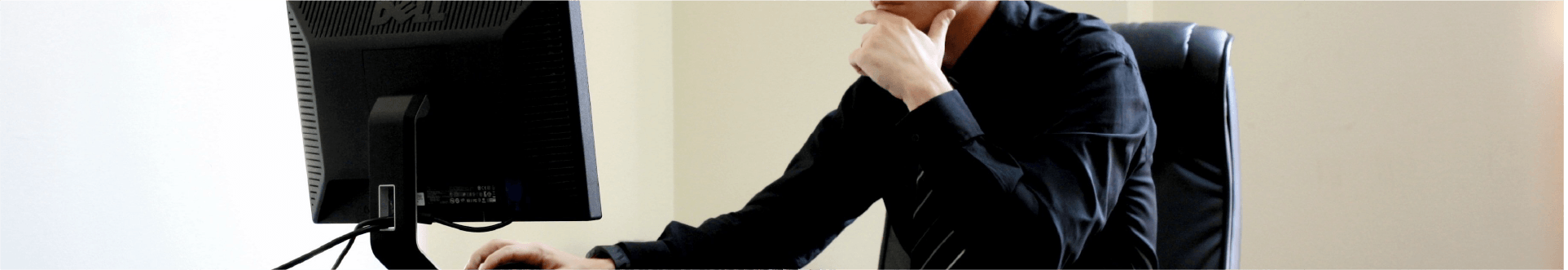 隠れ残業はPCログで防げる
隠れ残業はPCログで防げる
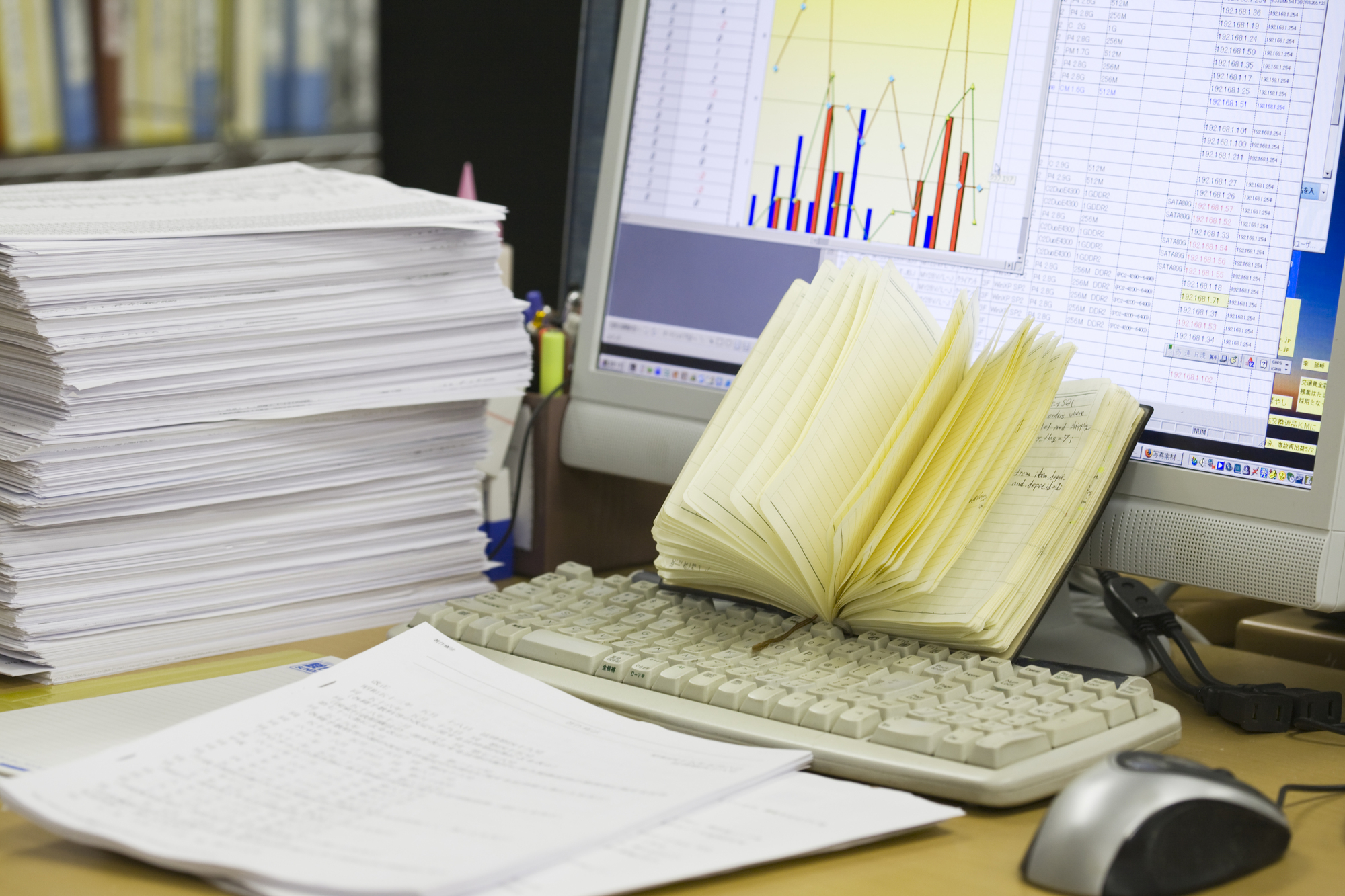
従業員の働き方が多様化する現代において、「隠れ残業」は多くの企業が抱える課題です。会社に申告されていない残業時間は、従業員の心身に負担をかけ、企業の生産性低下やイメージ悪化、さらには法的リスクに繋がる可能性があります。
特にテレワークやフレックスタイム制が普及したことで、どこで、どれくらい働いているのかが見えにくくなりました。知らず知らずのうちに隠れ残業が常態化しているケースも少なくありません。
そこで本記事では、この隠れ残業がどのようなものか、そしてサービス残業やさぼり残業とは何が違うのかを明確に解説します。さらに、隠れ残業がもたらす従業員と企業双方への悪影響を深く掘り下げるとともに、その防止策としてPCログを活用した労働時間管理の重要性と具体的な方法も紹介するので、人事関係者の方は、ぜひ参考にしてください。

「隠れ残業」という言葉は、仕事の効率化が叫ばれる現代においても、多くのビジネスパーソンが抱える問題を端的に表しています。単に長時間働くことではなく、その実態はより複雑です。ここでは「隠れ残業」がどのようなものか、定義や原因について以下の3つのポイントで解説します。
●隠れ残業の定義と具体例
●サービス残業やさぼり残業との違い
●隠れ残業の原因
隠れ残業とは、従業員が会社に申請した残業時間よりも、実際に働いた時間が長い状態を指します。申請された勤務時間には含まれないものの、業務遂行のために費やされた時間が隠れ残業にあたります。
ある調査によると、約25%のビジネスパーソンが、自宅に持ち帰って仕事をする「持ち帰り残業」や、残業代が支払われない隠れ残業を経験しています。その具体例として、以下のようなものがあります。
●持ち帰り残業:勤務時間内に終わらなかった仕事を家に持ち帰る
●早出:勤怠打刻をせずに、始業時間より早く出社して業務を始める
●テレワーク中の時間外労働:勤怠管理システムに記録されないまま時間外に作業する
●休憩時間中の作業:昼休みなど休憩時間に食事をしながら業務を続ける
残業のほとんどは、会社から命じられたものではなく、従業員自身の判断で行われることが多いのが特徴です。また、業務の延長線上で生じる雑務や事務作業を、プライベートな時間を使って処理することも隠れ残業に含まれます。
見えない残業である隠れ残業は「ステルス残業」と表現されることもあります。とくに、IT業界やクリエイティブ業界でステルス残業は増加傾向です。
隠れ残業と混同されがちなものが、サービス残業やさぼり残業です。サービス残業は、企業が意図的に残業代の支払いを避けるために、従業員の残業を記録させない、あるいは申請させない状況を指します。つまり、企業側の指示や暗黙の了解のもとで行われる違法な労働です。
一方、隠れ残業は、必ずしも企業に悪意があるわけではなく、従業員自身の責任感やプレッシャーによって、自ら残業時間を申告せずに仕事を続けるケースが多く見られます。具体的には、退勤の打刻後に業務を行う、残業時間を過少報告するなど、従業員が自主的に隠れて残業してしまうことを指します。
さぼり残業は、日中の業務時間を効率的に使わず、意図的に仕事を残業時間帯まで引き延ばす行動です。さぼり残業を防ぐためには、勤怠管理システムのログオン・ログオフ時間と、勤怠管理システムを連携させるなど、管理の厳格化が必要です。
職場以外の場所で業務ができるようになったため、実際の労働時間が見えにくくなり、隠れ残業がさらに増える傾向にあります。ただし、隠れ残業が発生する原因は、企業と従業員の両方にあります。
企業側の原因としては、以下の3点が挙げられます。
●過剰な業務量と人員不足
●長時間労働が美徳とされる風土
●労働時間の不適切な管理
勤怠管理システムが形骸化していたり、上司が部下の業務量や進捗を適切に把握できていなかったりした場合、隠れ残業は見過ごされやすくなります。また、残業申請をすると評価が下がるなどのプレッシャーも、隠れ残業につながるようです。
一方、従業員側の原因としては、以下の2点が代表的です。
●責任感の強さ
●残業ありきの働き方
仕事に対して強い責任感を持つ人は「最後までやり遂げなければならない」という思いから、サービス残業をしてしまいがちです。また「定時で帰るのは気が引ける」「周囲も残業しているから」といった考えから、特に必要がなくても残業をする習慣がついてしまうケースも少なくありません。
隠れ残業をなくすためには、企業側は適切な人員配置や業務改善を行い、従業員側は自身の働き方を見直す必要があります。また、企業と従業員が共に協力し、健全な労働環境を築いていくことも求められます。

隠れ残業は、従業員と企業双方に深刻な悪影響を及ぼします。一見すると個人の問題に思えますが、その根は深く、健康被害から企業の法的リスクまで、多岐にわたる問題を引き起こします。ここでは、隠れ残業がもたらす具体的なリスクについて詳しく見ていきましょう。
隠れ残業は、従業員の心身の健康と仕事に対するモチベーションに、以下のような悪影響をおよぼします。
隠れ残業が常態化すると、プライベートな時間や家族と過ごす時間が削られます。その影響として、生活の質や精神的な充足感が低下する悪循環が発生するのです。さらに、趣味や自己啓発に費やす時間がなくなり、心身ともに疲弊していくリスクが高まります。
見えない努力は、正当に評価されません。隠れ残業を続けても、その働きが会社に認められないと感じると、仕事への意欲は徐々に失われてしまいます。結果として、企業へのエンゲージメント(貢献意欲)が薄れ、モチベーションの低下を招きます。
過度な負担と、評価されないことへの不満が募ると、従業員は「この会社にいても報われない」と感じ始めます。最終的に、より良い労働環境を求めて離職を選択する従業員が増加し、会社の貴重な人材が流出する原因となるでしょう。
従業員の健康を害するだけでなく、隠れ残業は企業活動そのものにも大きな影響を与えます。その代表的なものが以下の4つです。
●生産性の低下
●企業イメージの悪化
●法的違反リスク
●情報漏洩リスク
疲弊した従業員は、集中力や判断力が低下します。これにより、業務効率性や品質が下がり、企業の生産性全体が低下します。隠れ残業によって業務が滞り、かえって業務効率が悪化するという悪循環に陥ることも少なくありません。
隠れ残業が常態化している企業は「労働環境が悪い」「従業員を大切にしない」といったネガティブなイメージを持たれがちです。社会的な信用を失い「ブラック企業」というレッテルを貼られると、採用活動にも悪影響です。優秀な人材の確保が困難になり、企業成長の阻害へとつながります。
隠れ残業は、労働基準法に違反する可能性があります。2019年4月1日から施行された「働き方改革関連法」では、残業時間の上限が厳格に定められました。たとえ従業員が自ら隠れて働いていたとしても、実労働時間と記録された時間に著しい乖離がある場合、企業は未払い賃金の支払いや罰金などの法的措置を受けることになります。
参考サイト:厚生労働省|働き方改革関連法」の概要
隠れ残業は、自宅などの職場外で業務を行うことも多いため、会社の機密情報漏洩のリスクが高まります。意図的でなくとも、不注意によって重要な情報が外部に流出する可能性も否定できません。

隠れ残業を防ぐためには、単に「残業を減らそう」と呼びかけるだけでなく、企業と従業員が一体となって具体的な対策を講じる必要があります。ここでは、隠れ残業を根本から解決するための防止策を3つ紹介します。
●労働時間ルールの明確化と周知
●固定業務の見直しと効率化
●PCログを活用した継続的な調査
隠れ残業防止のために、以下の2点に取り組むとよいでしょう。
●具体的なルールの明示
●法令遵守の徹底
ルールを明確化する具体策としては、労働時間の開始・終了時刻、休憩時間の取得方法、時間外労働の手続き(事前申請制など)を文書化し、全社で共有します。「会社から命じられた業務であれば、労働時間として記録されること」「残業の有無にかかわらず定時で打刻する」「〇時間以上の残業は申請禁止」といった、具体的かつ分かりやすいルールにすることがポイントです。
どのような状況がNG行為かを定義し、管理職含め全従業員と共有します。研修やパンフレットなどを利用して、繰り返し周知させ、ルールを浸透させていきましょう。
業務プロセスに非効率な部分がないか、定期的に見直すことも隠れ残業の防止につながります。そのためには、業務の棚卸しと再構築が必要です。従業員が日常的に行っている固定業務を洗い出し、自動化が可能なタスクや、必要性の薄れたタスクを特定しましょう。
次に、業務効率化のためのITツールを導入できないか検討しましょう。ワークフロー自動化ツールやプロジェクト管理ツールなど、ITツールを積極的に導入することで、手作業による非効率な業務を削減できます。
厚生労働省は、企業に「労働者の労働時間を適正に把握する責務がある」と明言しています。労働時間を適正に記録する方法としては、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録などによる「客観的な記録」が推奨されています。
その方法のひとつがPCログです。勤怠管理システムとPCログを連携させれば、打刻された勤怠記録と実際のPC稼働時間の照らし合わせが可能です。最適なツール導入が、法令遵守や安心して働ける仕組み作りの土台となります。
参考サイト:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

隠れ残業は、従業員と企業双方にとって見過ごせない問題です。この課題を解決するための手段として、PCログの活用が注目されています。PCログを隠れ残業防止に活用するメリットについて3つ紹介します。
●自己申告以外で労働時間を管理できる
●不自然な労働状況の早期発見ができる
●従業員の健康管理や公平な人事評価につながる
自己申告制では、打刻漏れや退勤後の残業による記録の修正といった手間が発生しがちです。しかし、PCログを活用すれば、PCの起動・シャットダウン時間から実際の勤務時間を推定でき、管理の手間を大幅に削減できます。
PCログとタイムカードの打刻時間や操作履歴を比較すれば、申告されていない労働時間を特定できます。例えば、打刻前の早出や退勤後の隠れた残業、休憩時間中の業務、さらには持ち帰り残業といった、見えにくい労働状況も可視化できるのです。
長時間労働が常態化している従業員をデータで特定できるため、疲弊する前に適切な介入や業務量の調整を行うことも可能です。これは、過重労働による健康被害を未然に防ぎます。労働時間の管理は公平な人事評価にもつながります。結果として、従業員のモチベーションや生産性の向上にも貢献するでしょう。

この記事では、隠れ残業の実態と防止策について解説しました。隠れ残業は、社内風土の変革と勤怠管理システムの構築の両輪で取り組むべき課題と言えます。PCログなどの管理システムを導入することは、隠れ残業の可視化に貢献するだけでなく、業務効率化やコンプライアンス遵守といった多岐にわたるメリットをもたらすでしょう。
ez-PCLogger(イージーピーシーロガー)は、PCログオン&ログオフ情報収集に特化した低コストなクラウドサービスです。ネットワーク未接続時のログオン&ログオフ時刻の記録ができるため、在宅ワークやシェアオフィスなど働く場所を選びません。
勤怠状況の把握だけでなく自己申告との乖離もチェックでき、サービス残業や長時間労働の防止に役立ちます。スタートアップから大企業まで様々な企業が導入しており、各種勤怠管理システムとの連携も可能です。トライアル期間中は、無料でご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。